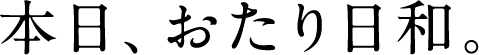- 地域づくり応援団が行く
- 農業
- 山の中を探検!田んぼの水はどこからくるの?
山の中を探検!田んぼの水はどこからくるの?
こんにちは!
小谷(おたり)村地域おこし協力隊の石田です。
先日、とある集落の田んぼの水がどこからやってくるのか山の奥まで探検に行ってきました。
雪もだいぶなくなり、いい天気!

午前中に行ったので、まだ気温で雪も緩んでおらず、かんじきもいりませんでした。
田んぼの上の山の中に続く1.5kmほどの道を、延々てくてく進みます。

イノシシの足跡らしきものを発見!

今の用水路の多くは掃除などの手間を考え、地中に埋まっています。
このように山の中を通る水路を「山腹水路」というそうです。
また、長野県では「用水路」のことを「せぎ(堰)」と呼びます。
春先に集落の皆で用水路の掃除をすることを「せぎ普請(ぶしん)」といいます。
現在でも、上流で水路にゴミがたまった時などにすぐに見に行けるよう、この水路の上の長い道のりは、春先みんなで草刈りをします。
一昔前(おじいちゃん、おばあちゃんが若かった頃)は、小谷村にもたくさんの人が住んでいて、見渡す限り田んぼが広がっていたとのこと。
反対の山を見れば地面が段々になっているのがよく分かりました。

こんな場所にも皆歩いてお米を作りに来ていたんですね。
さて、歩いていると…

道が崩れている…この景色、どこかで見たような…
そう、ここは井上(やきとり)さんが以前記事にしたあの、「シンプルな崖」です。
★まだチェックしていない方はこちらからご覧ください。
「街では体験できないクセがすごいおシゴト」
http://www.otari-biyori.com/articles/entry/cat/006914/
私も崖渡りの洗礼にあいました。

ひょえ〜〜スリリング〜〜
井上さんが命がけで作った小屋のおかげで、無事雪に負けず重機が守られていましたよ。


さて、出発から1時間ほど歩いて、ようやく取水の位置が見える場所までやってきました。
一番上まで行くことはできませんでしたが、「泥払い」を見ることができました。
このように、要所要所に掃除ができる場所をもうけてあるそうです。

耕作中田んぼに水がこなくなると、この場所まで掃除をしにきます。

途中、こんな場所も。
昔はこのつり橋の上を水のパイプを通していたみたいですよ。
おもしろい。

小谷村は「姫川」という水量の豊富な川が村で一番低い場所に流れており、集落はそれより標高の高い場所に位置しているため、山の深くの沢から水源をとる必要がありました。
今のように立派な重機のない時代に、山の奥から何kmにもわたる水路をつくる作業は、本当にたくさんの労力と時間と費用を必要としたそうです。
そのおかげで今があるんですね。
「稲刈り」と「田植え」だけではない”米づくり”。
小谷村には田んぼをお貸しする「田んぼオーナー制度」の取り組みがあります。
自然の中で一緒に農作業を楽しみませんか。
また、今年、平成30年9月8日(土)-9日(日)に「全国棚田(千枚田)サミット」が小谷村で開催されます。
興味のある方はぜひお越しください。
小谷(おたり)村地域おこし協力隊の石田です。
先日、とある集落の田んぼの水がどこからやってくるのか山の奥まで探検に行ってきました。
雪もだいぶなくなり、いい天気!

午前中に行ったので、まだ気温で雪も緩んでおらず、かんじきもいりませんでした。
田んぼの上の山の中に続く1.5kmほどの道を、延々てくてく進みます。
イノシシの足跡らしきものを発見!
今の用水路の多くは掃除などの手間を考え、地中に埋まっています。
このように山の中を通る水路を「山腹水路」というそうです。
また、長野県では「用水路」のことを「せぎ(堰)」と呼びます。
春先に集落の皆で用水路の掃除をすることを「せぎ普請(ぶしん)」といいます。
現在でも、上流で水路にゴミがたまった時などにすぐに見に行けるよう、この水路の上の長い道のりは、春先みんなで草刈りをします。
一昔前(おじいちゃん、おばあちゃんが若かった頃)は、小谷村にもたくさんの人が住んでいて、見渡す限り田んぼが広がっていたとのこと。
反対の山を見れば地面が段々になっているのがよく分かりました。
こんな場所にも皆歩いてお米を作りに来ていたんですね。
さて、歩いていると…
道が崩れている…この景色、どこかで見たような…
そう、ここは井上(やきとり)さんが以前記事にしたあの、「シンプルな崖」です。
★まだチェックしていない方はこちらからご覧ください。
「街では体験できないクセがすごいおシゴト」
http://www.otari-biyori.com/articles/entry/cat/006914/
私も崖渡りの洗礼にあいました。

ひょえ〜〜スリリング〜〜
井上さんが命がけで作った小屋のおかげで、無事雪に負けず重機が守られていましたよ。
さて、出発から1時間ほど歩いて、ようやく取水の位置が見える場所までやってきました。
一番上まで行くことはできませんでしたが、「泥払い」を見ることができました。
このように、要所要所に掃除ができる場所をもうけてあるそうです。
耕作中田んぼに水がこなくなると、この場所まで掃除をしにきます。
途中、こんな場所も。
昔はこのつり橋の上を水のパイプを通していたみたいですよ。
おもしろい。

小谷村は「姫川」という水量の豊富な川が村で一番低い場所に流れており、集落はそれより標高の高い場所に位置しているため、山の深くの沢から水源をとる必要がありました。
今のように立派な重機のない時代に、山の奥から何kmにもわたる水路をつくる作業は、本当にたくさんの労力と時間と費用を必要としたそうです。
そのおかげで今があるんですね。
「稲刈り」と「田植え」だけではない”米づくり”。
小谷村には田んぼをお貸しする「田んぼオーナー制度」の取り組みがあります。
自然の中で一緒に農作業を楽しみませんか。
また、今年、平成30年9月8日(土)-9日(日)に「全国棚田(千枚田)サミット」が小谷村で開催されます。
興味のある方はぜひお越しください。